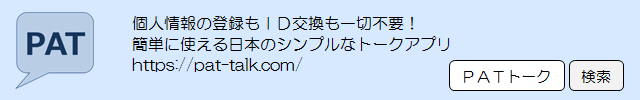書き方のコツ
では具体的にどのように記載していけば良いのか見てみましょう。
先ず最初に、会社の本業を最初に記載します。何をやる為の会社であるかということです。これを必ず1行目に書くようにしましょう。
これから興す会社が何をしたいのか分からない人はいないと思いますので(それもハッキリしないようなら止めた方が良いです)、漠然とした書き方ならすぐにできると思います。
例えば「イタリアンレストランをやりたい」「不動産屋をやりたい」「電気工事の下請け」「介護事業」「コンサルティング」……。まずはこの程度の骨格があれば良いです。その骨格に肉付けをして体裁を整えていく方法をここでは解説していきます。
同業他社を参考に
一番簡単なのは、同業他社の定款の例があればそれを参考にすることです。
大手企業の定款であれば洗練された書き方のものが多いですが、中小企業等ではあまりうまくない書き方をしているケースもありますので、何でもそのまま流用すれば良いという訳にはいきません。勿論、その書き方で登記できているのですから(どの法務局でも通るとは限りませんが)問題はないのかもしれません。但し、それが的確に業務内容を示し得ているか、対外的な信頼を得られているか、業務を広げる際に支障はないのか、必要な許認可を得るために十分であるか、といったことは別の問題です。
最近では具体性が問われなくなったこともあり、極めて適当な内容を乱雑に羅列している定款も多く見受けられますのでご注意ください。あくまでも他社事例は参考として捉えることも大事です。
書き方は2パターン
大雑把にまとめてしまうと、書き方には2つのパターンしかありません。実際の会社の定款をご覧いただければ分かるのですが、その殆どは2つの書き方に分類できます。
やや乱暴に思われるかもしれませんが、書き方としてはこの2つだけを意識しておけば良いでしょう。具体的には、
・ 『◎◎の△△』形式
・ 『(☆☆法に基づく)★★業』形式
の2種類です。
業種名そのものが業態を表すことができる場合は、後者の『★★業』という表記が有効です。法律で定められた範囲の業務を行う場合には、『☆☆法に基づく』と書くことで更に明確になります。
『◎◎の△△』という書き方はある意味万能です。「飲食店の経営」「健康器具の販売」など色々なケースに使えます。前半の「◎◎」の部分も後半の「△△」の部分も一つである必要はありません。「製造及び販売」のように並べることができます。「、」や「及び」で結びます。詳しくは個別ページで解説します。
「の」に代えて「に関する」という言葉も使い勝手が良いので、内容によってはこちらを使うこともできます。
許認可に注意
再三述べていることですが、許認可が必要な業種では、定款における事業の目的の書き方に制約がある場合があります。許認可を得る為には、それに適合した事業の目的を記載しておかなければなりません。
この点を疎かにしてしまうと、実際に許認可を得て事業を始める為に定款変更の手続きが必要になってしまいます。定款変更は煩わしいだけでなく、登録免許税だけで3万円かかりますのでご注意下さい。