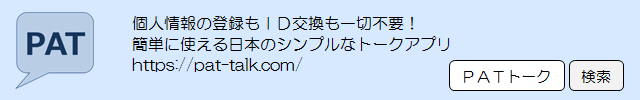書き方の決まり
会社を設立するにあたっては法人としての登記が必要となりますが、登記申請をすれば全て受理されるというものではありません。申請した書類は登記所による審査を受けることになります。定款が正しく作成されていることも当然ながら審査されます。ここでは「事業の目的」の書き方について、現在の会社法に基づいて解説していきます。
旧商法の下では、事業の目的には「営利性」「適法性」「明確性」「具体性」が必要であるとされて来ました。しかしながら、会社法では類似商号規制が廃止されたことから、登記官による事業目的の審査の対象として「具体性」は必要な要件から外れることになりました。
法務省「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」には、「会社の設立の登記等において,会社の目的の具体性については,審査を要しないものとする。」とあります。
もう少し詳しく解説すると、旧商法における「類似商号規制」では同一市町村においては他人が登記した商号を同一の営業のために登記することはできないことになっていました。その為に事業の目的に具体性が求められていました。現在の会社法ではこのような規制はなくなり、同一の所在場所において同一の商号でなければ良いことになっています。
では、まずは「営利性」「適法性」「明確性」について詳しく見てみましょう。
営利性
会社は利益を上げることを目的としていますので、事業の目的には当然ながら営利性が求められます。
実は会社法では営利性を有さない事業を行うこともできるようになっていますが、利益を生む可能性のない事業を目的として掲げることは不適切と解されています。
「寄附」「政治献金」「ボランティア活動」などは(勿論会社として行うことはできますが)事業の目的としてふさわしくありません。
適法性
当然のことですが、事業の目的は法令や公序良俗に反しているものであってはなりません。
「殺人及び傷害の請負」「売春の斡旋」「覚醒剤の取引」などといった事業の目的は認められません。ここまで極端でなくても、法令に違反している行為でないことは確認しておく必要があります。
法令で弁護士や司法書士、社会保険労務士などの士業の資格者にのみ認められている独占業務を事業の目的とすることはできません。
明確性
明確性というのは少し難しいかもしれませんが、一般に理解できる語句を用いて内容が判断できるように記載するということです。
一般に理解できる語句としては、通常の国語辞典(広辞苑等)や現代用語辞典(イミダスや現代用語の基礎知識等)に記載されていることが一つの目安として判断されています。業界内だけで通用するような専門用語等は一般には理解できないことから明確性を欠くものとされます。この基準は明確に線を引くことは難しいですが、ある程度社会に認知されている言葉を選ぶようにすると良いでしょう。
具体性は全く必要ないのか?
先に述べたように、具体性は登記における審査の要件から外れました。従って、「商業」「工業」「商取引」「適法な一切の事業」などという書き方も事業の目的として認められるようになってはいます。
しかしながら、このような書き方はやはり避けるべきです。これでは何の会社であるかサッパリ分かりませんし、対外的な信頼を得ることはできません。特に金融機関の審査等では著しく不利になります。
許認可が必要な業種では特に注意が必要です。